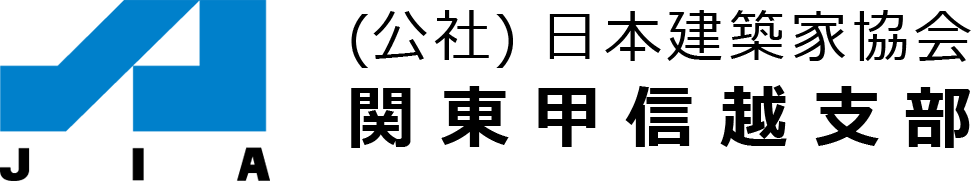■今年1月に、2008年度のJIA日本建築大賞の公開審査が実施され、北川原温氏の中村キース・ヘリング美術館が選出されました。これを受け、今回インタビューをさせて頂くこととなりました。インタビューに先立ち、自宅内の茶室にて、奥様にお茶を点てて頂きました。お茶を頂きながら、すっかりと和んだムードになり、事務所会議室にてインタビューがスタートしました。
――改めまして、JIA日本建築大賞受賞、おめでとうございます。
今回の中村キース・ヘリング美術館において、今までと違う新しい試みや取り組みなどがありましたら、お聞かせ下さい。
そうですね、他のプロジョクトとちょっと違うのは、やっぱりアメリカのニューヨークという、ちょっと特殊な大都市で地下鉄の落書き、つまり社会への批判と反抗から始まったキース・ヘリングというアメリカン・グラフィティの最初の人、そういう人の作品を展示する美術館を日本につくるという、その辺が一番ほかの仕事と違うところだと思うんですね。
なぜ美術館を建てることになったかなんですが、クライアントがコレクターで、家中キース・ヘリングだらけなんです。家にやってくる人たちに「もっとたくさんの人に、見てもらった方が良いのでは」と勧められて、美術館をつくろうということになったんです。さて、どこにつくるかということで、ニューヨークか東京かで検討していたのですが、昔のように、大都市の地下のエネルギーが充満しているような、今はそういう時代ではなくなってきていて、ニューヨークも危ない場所はなくなって綺麗になってしまい、東京は元々そうだし……。
そうしたなか、たまたまクライアントが山梨県の小淵沢に土地をいっぱい持っているのですが、キース・ヘリングの話とは関係なく、小淵沢に連れて行かれて「別荘とか何か面白いものできないかなぁ。」と言われたんですね。小淵沢の穏やかで爽やかな自然の中を歩いていて、その時にね、ここにキース・ヘリング美術館を作ったら面白いかも知れないなって思ったんですね。
でも、それを言うとクライアントに北川原は頭がおかしいんじゃないかと思われると思って、黙っていたんです。でも僕の中ではだんだんと、それがリアリティを持ってきてしまって、なぜかと言うと、小淵沢は八ヶ岳の麓なんですけど、あの八ヶ岳の南斜面一帯というのは縄文人が、大集落をつくっていたところなんですね。
現代人に比べれば遥かに豊かな野性と言うか、自然そのものだった縄文人はどんな生活をしていたのか、その深い原始性、プリミティブだけどある激しさをもったイメージが、僕の中ですごくキース・ヘリングに近づいていったのです。また、発掘された土器の写真集を見ていたら、キース・ヘリングのドローイングにそっくりな土器があって、人間の形がレリーフになっているんです。それで、キースと縄文が繋がってしまったんです。ある日、クライアントの中村さんとご飯を食べている時に、なんとなく話をしやすい雰囲気になったので言ったんです。「この間見た小淵沢の土地、あれいいですよね。あのあたりはすごかったんですね、縄文文化が。
土器のかけらがあちこちから出るって聞いて驚きました。キース・ヘリングも壺をつくっているんですが、そこに人の絵が描かれていて、縄文土器とそっくりなんです!」そうしたら中村さんが、「いやー北川原さん、僕ね、同じものを博物館で見たんだよ!それでね、ピンときたんだ、これはいけるってね!」と。同じことを考えていたんですね。
そういう時間が1、2ヶ月以上あったのですが、とても大事な時間だったような気がします。それからどんどんイメージが膨らんでいって、例えば縄文の闇とキースの闇が重なって「キース・ヘリングって、やっぱり闇が要るなぁ」っていうような話になって、アプローチもだんだん暗闇に入っていくような空間になったんです。ただ、教育委員会がなんて言うか心配でした。
竣工式には、県知事や市長、教育長や教育委員会の人たちも来ました。暗闇の展示室だけでなく、展示の絵も、中にはかなりきわどいものもありますし気がかりでした。しかし中村さんは、キース・ヘリングの本質はそういう闇の部分にあり、いわゆるポップアートと呼ばれた、
人の形の増殖パターンみたいなもの、その無限に続くドローイングの中に、生命の尊厳とか、脆さとか、紙一重の狂気と理性や不条理が潜んでいると言うんですね。
だからこそエネルギーを感じる、野性の原始の輝きのようなもの、というのが中村さんの解釈なんです。キースはエイズで32 歳で死んだのですが、自分の命の限界を見据えた上で、作品づくりをしていたんですね。そういうものが根本にあって、闇の展示室には、かなりきわどいドローイングの展示を、中村さんは希望していたわけです。
そうして、教育委員会の人たちにも、竣工式の内覧会で、「感動しました。中村さんのつくった美術館の考え方がよくわかりました」と賛意をいただき、「こういう作品は、積極的に子供達にも見てもらっていくべきでしょう」とまで言ってくれた委員もいたのです。
―― 建築界全体において、新しい試みや取り組みの必要性を感じているものがありましたら、お聞かせ下さい。
JIA日本建築大賞の公開審査なのですが、当日、寝不足気味だったこともあり、自分のプレゼンの番で緊張が緩んでいたせいか、プレゼンテーションというよりも、僕の前にプレゼンをした何人かの候補者の感想のような話をしてしまいました。
ほとんどの人たちのプレゼンテーションは、問題解決型でした。こういう問題があって、その問題を解決するのに、こういうデザインを考えました。それが小さく見えたのです。それは、今の日本の建築の、閉塞的な状況のひとつなのではと。
もっと根本的なことに目を向けないといけないのではと思ったのです。プレゼンテーションが終わり、審査員の議論が始まりました。三人のうちのお二人は、非常に俯瞰的に講評をされていて、建築界全体を審査しているようにも感じました。あるひとりの建築家にしかできないものを創ることも、レーゾン・デートルだという考えがありますが、私もそうだと思うのです。
百人の建築家がいれば、百の違う建築が生まれるわけですね。それが今この時代に、非常に弱くなっているというか、薄まっていて似てきている、と仰っていたと思います。
また、一人の審査員の方が、「強い建築を創ることが大事だ」と言っていたような気がします。やっぱり建築は社会や周辺環境に影響を与えていく、そういう強さが必要であると。それは大きいとか表現が力強いとかいうことではなくてね。戦略のことなんですね。
―― 一般社会における建築家の位置付けや認知について、どのようにお感じでしょうか?
建築家というのは、非常にバランス感覚を必要とする職業だと思います。本当に、色々なことを勉強していますよね。だから、もっと建築家が活躍して、社会のリーダー的なポジションで、どんどん発言するべきだと思うのです。ところが今、使われるという風になっているんですね。
馬場璋造さんが最近出された本があって、建築家というのは信用で仕事をするのではない、信頼で仕事をするのだと書かれています。私も、その通りだと思います。
信用とは違い、信頼となると、全人格が問題になってくる。その信頼を得て、仕事をしなければならない建築家というのは、すごく大変なわけで、その重責に対する理解や経済的な対価というものも、日本はあまりにもひどいと思うのです。本当に、そこを何とかしないと、いつまでたっても建築は文化にならないという感じがします。
―― 一連の建築基準法改正があのような状況になっていて、行政の人達自身がどうして良いかという場面があります。このような状況に対するご意見をお聞かせ下さい。
そうですねー、基準法の問題は大きいですよね。自分で作って、 自分で苦しんでいるような感じで、マゾヒスティックな感じすらします。どんなに素晴らしい文化が育とうとしても、それを潰そうとしているように思えてしまいます。当事者の中にはそれをわかっている人もいると思うんですけど……。
――造形ということについてですが、どのように意識されているのでしょうか。
学生時代なんですが、記憶違いでなければ、村野藤吾氏の書いた本か、あるいはインタビューを受けた記録だったか、そこには、「私のクライアントが、私の鉛筆で描く一本の線に、3億円をかけるのです」という主旨のことが書かれていたんです。
すごく印象的だったんですが、その時は意味がわからなくて。その一本の線に重みや意味があって、そしてそのことを実感としてだんだんと感じるようになってきたんです。
そして、39 歳の時にメトロサという作品でJIA の新人賞を頂いたんですが、首にかけてもらったメダルが、ブロンズの塊ですごく重かったんです。重量が重いだけじゃなくてね(笑)。それからスケッチにしても、すごく慎重になってしまって、形に関してはなかなか決められません。
――現在、木造は取り組まれていますか。
新しい木造システムなど考えています。稲荷山養護学校では、岐阜県立森林文化アカデミーでの面格子構造とは違っていて、柱と梁を2 本ずつ抱き合わせたものです。なぜ2 本かというと、小径の間伐材を使うので、それらを組み合わせて強度を出すためなんです。全部、長野県産の唐松で、出どころが全部明記される認証システムを確立しました。
――間伐材を積極的に使おうということでしょうか。
森を健全な状態に維持するために必要です。唐松はクセが強くて扱いづらいのですが長野県では唐松の利活用の研究が非常に進んでいます。
―― ステファヌ・マラルメの詩をお話されることがありますが、いつ頃、知ることになったのでしょうか。
大学1年生の時、よく神田の古本屋に通ったのですが、まずその時に、ロートレアモンの『マルドロールの歌』という本に出会い、大変な衝撃を受けました。マラルメの詩の中で一番驚いたのは『骰子一擲』という詩で、サイコロの一投げするという意味なのですが、30 歳を過ぎてこの詩が建築そのものだということを知ったのです。建築は、関係性の織物と言う空間をもっていますが、この詩はまさにそういう空間をもっているのです。そして、マラルメもロートレアモンの詩も、今でも何か困った時などに読んで気持ちをリセットしています。
■穏やかで物静かな印象があった北川原さんですが、インタビューが始まると非常に気さくにお話し頂き、終始、笑いの絶えない場となっていました。時には静かに、時には熱く語って頂き、日々の設計活動で忘れてしまいそうな原初の部分を、建築は強くあるべきかを、ハッと思い出させられる場面もありました。

「中村キース・ヘリング美術館」/パーティコートより見る。
[撮影:大野繁] |

右端の黒い倒立円錐の内部は闇の展示室への入口。
[撮影:大野繁] |
|