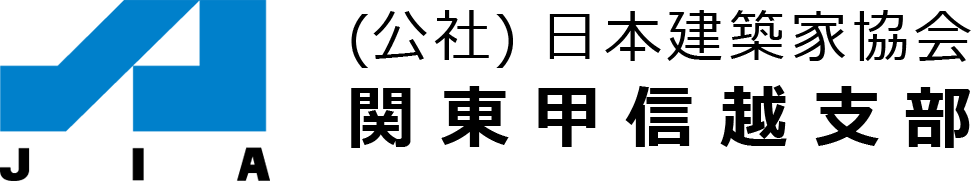フィジーに本拠を置く南太平洋大学の情報通信技術センター(Japan-Pacific ICT Centre)の基本設計調査を独立行政法人国際協力機構(以下 JICA)の依頼で2005年2月に実施した。その4年後の本年1月21日、このセンターの起工式が行なわれ、プロジェクト責任者として出席した。本来であれば2006年に着工するはずであったが、クーデターなどの影響から2年遅れとなった。
今年の1月のフィジーは豪雨による洪水の被害が拡大し、離島への観光拠点で国際空港があるナンディから首都スバへの道路が寸断された。そのため、いつもの陸路をあきらめ空路を使った。首都スバ郊外の空港もしばしば冠水し、空港が閉鎖されるとのことだが、私は幸運にも時間通りに到着した。先にフィジー入りした関係者はナンディで一時避難のため宿泊したホテルが陸の孤島になり、数日足止めをされたとのことだった。私は 20回近くフィジーを訪問しているが、初めての経験である。フィジーにも温暖化の影響が拡大しているようだ。
政府開発援助(ODA)
私は設計活動の三分の一に当たる約15年間をJICAが実施する政府開発援助(ODA)のプロジェクト責任者としてアフリカ、南米、大洋州、東南アジアなどで計6カ国にかかわってきた。
ODA ではプロジェクト責任者が基本設計調査から工事完成まで責任を持つことが常で、建設プロジェクトの場合、完成は早くても3年を要する。依頼されるターゲット分野はあらかじめ示されるが、敷地の選定も対象となることもあり、約1ヶ月間の現地調査で相手国と実施方針の協議を重ね、覚書を取り交わす。帰国後、実施の可否も含め、関係者が納得する形で最も効果的な事業内容の結論付けが求められる。運営に必要な機材の調達や完成後の運営上の問題点の解決方法も業務に含まれる。
ODAプロジェクトは白紙に近い状態から計画を組立、総事業費の算出や工事入札業務も含まれ、国内の通常業務との違いがある。プロジェクトの実施は基本設計報告書を元に閣議で決定され、二国間で交換公文(E/N)を結び、日本の会計年度に従い、実施される。

|

ナンディ空港付近の洪水 |

12 の島嶼国のキャンパスを結ぶ USPNet |

フィジーの USP 本部のパラボラアンテナ |
南太平洋大学
この大学は 1968年に12の島嶼国・地域(フィジー、 クック、キリバス、マーシャル、ナウル、ニウエ、ソロモン、トケラウ、トンガ、ツバル、バヌアツ、サモア)が共同設立し、当初から短波ラジオで遠隔教育を実施してきた。
USPは1990 年初頭に太平洋島嶼国で初めてE-mailシステムを導入した。2000年にはJICAの支援で衛星通信を利用した音声、データ回線とビデオ回線を用いる USP Netを完成させ、映像を利用した遠隔教育を実施してきた。その後、2005年から2006年にかけて衛星通信のインターネット・プロトコル(IP)化と増速を行なった。
総学生数は21,131人(2006年)、フルタイム学生は 約11,445人(2006年)、大学に定期的に通学する学生 は約55%で、残りの45%はフィジー国内僻地や各島嶼国のキャンパスで ICT を利用して学習をしている。
JAPAN-PACIFIC ICT CENTRE の計画
このセンターの計画は2003年5月に沖縄で行なわれた第3回太平洋・島サミット(South Pacific Forum)で合意されたデジタル・デバイド(情報格差)の軽減にかかわるプロジェクトである。主な施設内容はコンピュータ科学科のコンピュータ実習室、ITサービス部のサーバー室やUSPNetコントロール室、産学協同が期待される研究・開発部、工学科の通信技術の実験室、共用の多目的講堂と教職員室である。施設規模は地上2階〜4階建約 6,660m2の施設で、キャンパスの北西部の丘陵地にシンボリックに位置し、大学の中心的な建物となる。 建物外観はPCシリンダー型枠の列柱をデザイン基調とし、コンピュータが設置される箇所以外は自然通風とするため、列柱の内側にはバルコニーを配置する方針とした。多目的講堂の正面は設立メンバーをイメージする12本の列柱を配し、壁面は12カ国固有のタパクロ スの紋様をモザイクタイルで表現する計画である。 完成後のセンターは、USPの遠隔教育をグレードアップし、島嶼国固有の文化をデジタル化して配信・保存する活動拠点となる。さらに宇宙航空研究開発機構の超高速インターネット衛星「きずな(WINDS)」による教育や医療などの情報通信の実証実験の拠点としても活用され、島嶼国におけるデジタルデバイドの緩和に貢献し、社会経済の開発促進に寄与することが期待される。
 |
 |
 |
モニターが並ぶ現在のUSPNet
コントロール室 |
コンピュータラボで自習する学生 |
講義室での真剣な学習風景 |
 |
 |
 |
起工式で12カ国の中央に立つ
日本の国旗 |
左より学長、国土大臣、
日本国大使、筆者 |
鍬入れ式は9名で行なわれた |
 |
 |
 |
| 様々な行事が行われるキャンパスの広場 |
完成予想図
(右の多目的講堂は計画中) |
広場より工事が始まった敷地を望む |
|